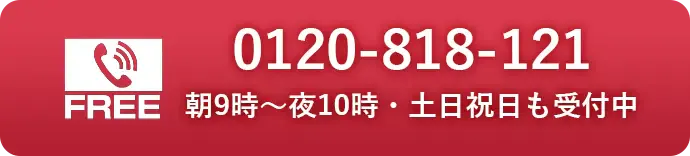- 事故のケガにより、予定していた旅行をキャンセルしました。キャンセル料は補償されますか
-
交通事故によるケガが原因で旅行に行けなくなった場合に、キャンセル料が損害として認められるケースがあります。
ただし、キャンセルの理由に事故との相当因果関係がなく、キャンセル料を支払っても旅行を取りやめる状況ではなかったと判断された場合は損害として認められません。
また、被害者以外の同行者のキャンセル料を損賠として請求できるかは、本人と同行者の関係性、旅行の目的や行先など個別の事情によって異なります。
- 傷害事故の場合、入通院を強いられたことに対する慰謝料がもらえると聞きましたが、どのように算出するのでしょうか?
-
慰謝料は、被害者が交通事故によって精神的または肉体的に被った被害によって精神的に感じた苦痛に対する損害です。受傷の慰謝料は、受傷の部位、程度、入通院期間の長短に従って、ある程度、定額化して慰謝料額を算出します。裁判上では基本的に下記の別表Ⅰ・Ⅱの表を用います。
別表Ⅰ 他覚症状がないむち打ち症以外の傷害の場合に適用する表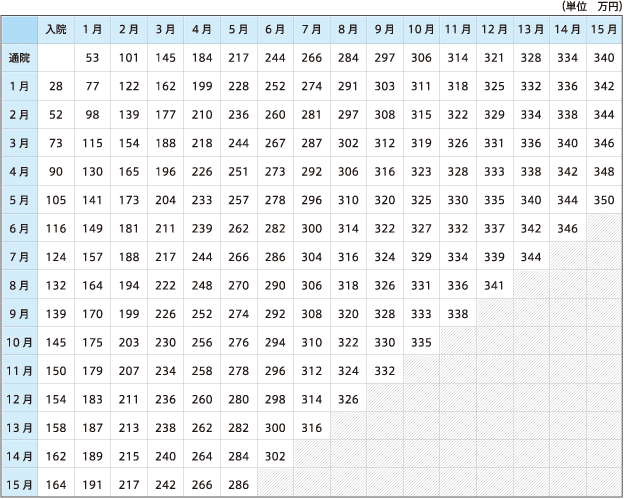
別表Ⅱ むち打ち症で他覚症状がない場合に適用する表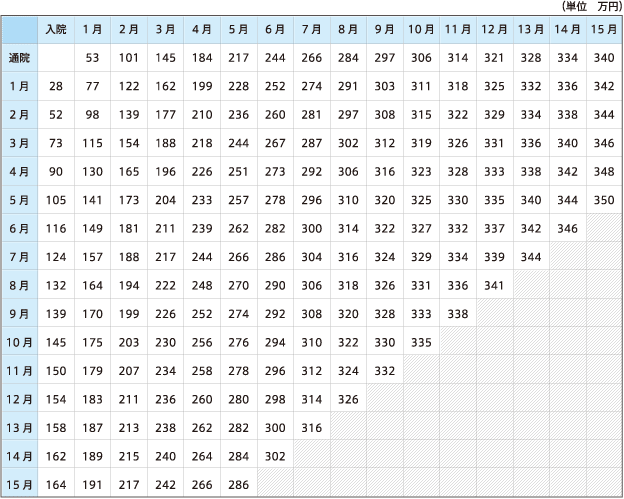
(1)傷害慰謝料については、原則として入通院期間を基礎として別表Ⅰを使用する。
通院が長期にわたる場合は、症状、治療内容、通院頻度を踏まえ、実日数の3.5倍程度を慰謝料算出のための通院期間の目安とすることもある。
被害者が幼児を持つ母親であったり、仕事等の都合など被害者側の事情によりとくに入院期間を短縮したと認められる場合には、上記金額を増額することがある。なお、入院待機中の期間およびギプス固定中等安静を要する自宅療養期間は、入院期間とみることがある。(2)傷害の部位、程度によっては、別表Ⅰの金額を20~30%程度増額する。
(3)生死が危ぶまれる状態が継続したとき、麻酔なしでの手術等極度の苦痛を被ったとき、手術を繰り返したときなどは、入通院期間の長短にかかわらず別途増額を考慮する。
(4)むち打ち症で他覚症状がない場合などは別表Ⅱを使用する。通院が長期にわたる場合は、症状、治療内容、通院頻度を踏まえ実通院日数の3倍程度を慰謝料算定のための通院期間の目安とすることもある。
<適用上の注意>
入院のみの場合・・・入院期間に該当する額
通院のみの場合・・・通院期間に該当する額
入院後に通院があった場合・・・該当する月数が交差するところの額通院慰謝料は、隔日通院の原則を示す。したがって、通院実日数が隔日通院より多い場合または少ない場合には、適宜増減して認定する。
入・通院期間に1ヶ月未満の端日数が生じた場合、その端日数については、各期間別慰謝料の金額を日割計算する。”
- 自賠責保険によって賄われる慰謝料はいくらですか?
-
自賠責保険で賄われる部分は、原則として、4,300円×通院実日数の金額となります。
その他、
【1】『治療実日数×2<治療期間』の場合は、「治療実日数×2」が対象日数(通院実日数が10日、治療期間が50日だった場合 4,300円×10日×2=86,000円)、
【2】『治療実日数×2>治療期間』の場合は、「治療期間」が対象日数(通院実日数が10日、治療期間が18日だった場合 4,300円×18日=77,400円)
という計算になります。
- 死亡事故の慰謝料は、どのように算出するのでしょうか?
-
死亡事故の慰謝料としては、亡くなった本人の慰謝料と近親者の慰謝料がありますが、亡くなった本人の慰謝料請求権を相続人が相続する結果、相続人である近親者は本人の慰謝料と自身の慰謝料をまとめて請求することになります。そして、裁判所基準(裁判をしたならば認められる基準)については、被害者が一家の支柱の場合2,800万円、母親・配偶者の場合2,500万円、その他の場合2,000万円~2,500万円と、一応の目安が決められています。死亡慰謝料は、被害者本人はもちろん、被害者の死が遺族に与える精神的な苦痛の大きさを考慮して算出します。
自賠責保険会社の基準では、【1】死亡した本人分400万円(※)+【2】被害者の父母、配偶者および子の分(それらが1人の場合は550万円、2人の場合は650万円、3人以上の場合は750万円となり、さらに被扶養者がいる場合は200万円が加算されます)となります。自賠責保険基準 任意保険(参考)基準 一家の支柱 400万円(※) 1,500万円~2,000万円 18歳未満 (幼児・児童・学生) 400万円(※) 1,200万円~1,500万円 高齢者 (65歳以上) 400万円(※) 1,100万円~1,400万円 上記以外 400万円(※) 1,300万円~1,600万円 自賠責保険の場合、本人の慰謝料400万円(※)に遺族の慰謝料が加算されます。 遺族の慰謝料
請求権者1名の場合550万円、2名の場合650万円、3名以上の場合750万円。被害者に被扶養者がいるときは、さらに200万円が加算されます。
※自賠責保険の支払基準改正により、2020年4月1日以降に発生した事故については、死亡した本人への慰謝料額は400万円に変更となりました。なお、2020年3月31日以前に発生した事故については、従前のとおり、死亡した本人への慰謝料額は350万円のままとなります。
- 入通院慰謝料という項目ではなく、精神的苦痛による慰謝料として請求することはできるのですか?
-
交通事故の被害に遭われた方のお気持ちはよくわかります。しかし、症状固定日までの精神的苦痛は、入通院慰謝料として評価し尽くされていると考えられていますので、入通院慰謝料とは別に精神的苦痛による慰謝料を請求することはできないのが原則です。
- 加害者や相手の保険会社からまったく謝罪がないし、誠意も感じられません。それらの点について損害賠償を請求することはできるのですか?
-
交通事故の被害に遭われた方のお気持ちはよくわかります。しかし、加害者や相手の保険会社からまったく謝罪や誠意がない場合であっても、それらの点について、損害賠償を請求することは難しいです。
- 事故のケガにより会社を解雇され、解雇を理由に婚約破棄になりました。婚約破棄に対する慰謝料を請求できますか?
-
交通事故以外に婚約破棄の理由がないということであれば、慰謝料が認められる可能性があります。ただし、解雇や婚約破棄に正当な理由がない場合には、事故の加害者が賠償すべき損害ではないということもできるので、認められるかどうかは、非常に難しい問題です。
- 後遺障害の判断はどうやってされるのですか?
-
症状固定後に、医師に認定基準に従った後遺障害診断書(用紙は損害保険会社にあります)を作成してもらいます。後遺障害診断書は、作成に1週間~10日程かかる場合もありますので、なるべく早く作成してもらいましょう。そのうえで後遺障害診断書を添えて、後遺障害の認定を申請します。方法は以下の方法があります。
1.被害者請求
被害者請求とは、後遺障害診断書と受傷時のX-P(レントゲン)・CT・MRI、症状固定時のX-P・CT・MRIを医療機関から被害者自身が貸し出しを受け、加害者の加入する自賠責保険会社に対して後遺障害等級の認定申請をする方法です。
被害者請求の場合は、等級の認定通知が直接被害者になされ、また、一定の金額が直接被害者の口座に振り込まれます。
2.事前認定
事前認定とは、加害者の加入する任意保険会社に後遺障害診断書を提出し、依頼する方法です。ほとんどの被害者の方はこの事前認定を行っているのが実情です。
事前認定の場合は、等級の認定通知は任意保険会社になされ、被害者は任意保険会社から等級の認定通知を受け、その等級に基づく損害賠償額で合意しないかぎり、お金は振り込まれません。
この場合でも、認定自体は、損害保険料率算出機構の調査事務所が行います。
- 顔面醜状の場合、労働能力喪失率はどの程度なのでしょうか?
-
顔面など外貌に醜状が残った場合は、手足や身体に機能障害が残った場合などとは違い、身体的機能そのものに支障が生じるわけではないので、直接的には労働能力が喪失したとはいえない場合があります。しかし、芸能人・モデルなど、外貌が重要な職業に就いている場合に限らず、外貌醜状が残ったことで、就ける職業・職種が限定されたり、仕事に何らかの支障が出たりするおそれが高いことを理由に、逸失利益が認められる場合があります。
なお、逸失利益の算出に必要な労働能力喪失率は、認定された後遺障害等級によって異なり、下記の表が目安となります。しかし、外貌醜状の場合、等級認定表に定められた労働能力喪失率どおりには逸失利益を算定しないことがありますので、そのような際は、粘り強く任意保険と交渉することが必要です。外貌醜状の後遺障害等級と労働能力喪失率の目安
後遺障害等級 労働能力喪失率 7級12号 56% 9級16号 35% 12級14号 14%
- 家族が交通事故にあい、外傷性くも膜下出血、びまん性軸索損傷と診断されましたが、のちに高次脳機能障害だとわかりました。後遺障害等級の認定は受けられますか
-
高次脳機能障害は、交通事故や転倒などによる外傷性脳損傷や脳血管障害・脳腫瘍・脳炎・低酸素性脳症などの疾患により発症します。高次脳機能障害は脳の一部が損傷を受けることで、記憶、意思、感情などの機能に障害が現れる傷病です。受傷・発症後、身体的な後遺症を残さない場合が多いため、外見上障害があることがわかりにくく、一見健常者との見分けがつかない場合もあり、そのため周囲の理解を得られにくいといった問題もあります。また、障害の程度によっては本人ですら指摘されるまで気づかないということもあります。
高次脳機能障害とは脳の機能の中でもとくに高度な機能の障害です。そのため、交通事故による受傷の場合に、事故による後遺障害として認めてもらうためには、まだまだハードルが高い障害といわれています。病院で高次脳機能障害の確定診断をされた方を含めて、高次脳機能障害として後遺障害等級の認定を受けようとする場合、他の障害の立証も含めて、申請は慎重に進める必要があります。高次脳機能障害自体の立証についても、実際の症状に応じた後遺障害等級の認定を受けるには、適切な検査・診断と申請書類の作成および添付する医証が大きなポイントになります。高次脳機能障害の等級はおよそ以下のとおりとなります。
中枢神経系の障害(従来の脳損傷)の後遺障害等級
障害認定基準 別表第11級1号 「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの」 別表第12級1号 「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの」 別表第23級3号 「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの」 別表第25級2号 「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの」 別表第27級4号 「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの」 別表第29級10号 「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの」
まずはお気軽にご相談ください。
朝9:00 ~ 夜10:00・土日祝日も受付中
0120-818-121